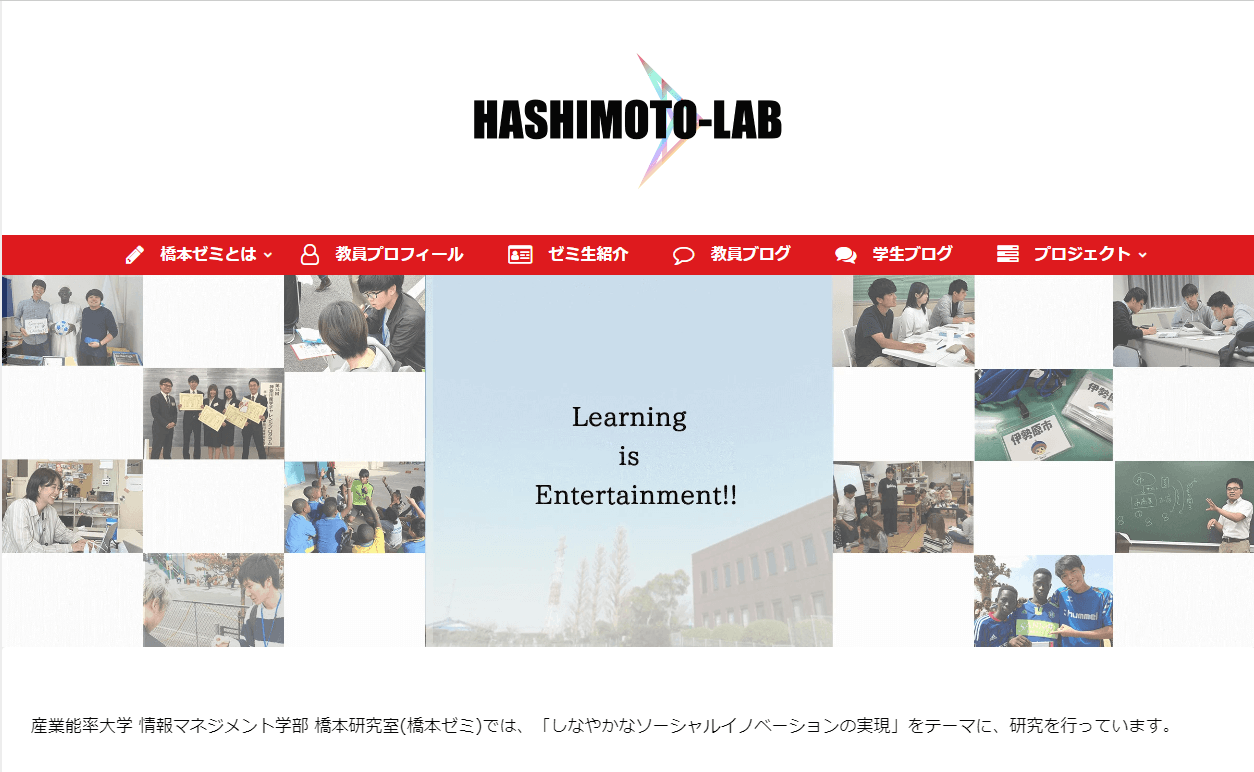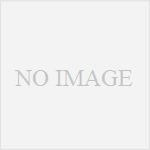本書は、OECDが発表している「Recognising Non-Formal and Informal Learning: Outcomes, Policies and Practices」の翻訳版である。
学習と言えば、学校教育に代表されるFormal Learningがすぐに想像されるが、人は学校だけで学ぶ訳ではない。家庭の中、仕事、アルバイト、遊びを通じても学習している。また、学校においても授業だけですべてを学んでいるわけではなく、学園祭の企画などの人間関係を通じて協調的に物事を進めることを学んでいたりする。そういったformalではない学びについて、Informal LearningやNon-formal Learningとよんでいる。
本書は、そんなインフォーマルラーニングやノンフォーマルラーニングをいかにして、可視化し、社会的に認証しようとしているのかについて国際調査の結果をまとめたものである。各国それぞれの理由で(決して同一ではない)、この課題に取り組んでいるし、同時に苦労もしている事がよくわかった。
大学や企業内教育に所属される方は、一通りどのような世界があるのかについて目を通しておいた方が良いかと思う。
目次
大学における意味
本書が提示しているインフォーマルラーニングやノンフォーマルラーニングの可視化や認証というものの大学という機関においての意味は、2通りあると思う。
一つは、フォーマルラーニングの限界とでも言うべきものである。本書では、「仕事をするための能力においてノンフォーマルやインフォーマルラーニングが果たす貢献が大きい事を示しており、それ故に如何に認証をするのかが重要である」という観点になっている(ように思える)。
つまり、フォーマルな教育は、それだけでは偏ったものになるということだ。現在、広がりを示しているアクティブラーニングや、PBL(プロジェクトベースドラーニングやプロブレムベースドラーニング)というのは、フォーマルな教育に、如何にインフォーマルな要素を入れていくのかということであり、こうした現状に対する策のひとつといえるだろう。逆にいえば、こういった手法を取り入れる事はある種必須とも考えられる。
もう一方では、大学としての貢献先は誰なのか、という事が問われている。
ノンフォーマル・インフォーマル学習の認証は、伝統的なルートで大学に入れなかった人に高等教育や大学に入学する方法を提供する。おそらくこれが最も顕著に当てはまるのは、入学の前提条件の免除であり(後略)P77
上記の指摘の通り、実はインフォーマルな学習を認証することは、大学の潜在顧客を広げる事につながるというのだ。少子化が進む中では、大きな機会ともいえるだろう。当然、今までとは違った教育機会を提供する事が必要になるし、教育方法(eラーニング等の通信教育)が必要になるといえる。
企業における含意
企業においての含意としては、フォーマルな教育歴だけを評価するのではなく、何らかの手法によりその他の経験についても評価をする事は、自社の人事戦略上有効だといえる事である。
フォーマルな教育歴とは、すなわち学歴のことである。確かに学歴の高さと仕事の出来には相関関係があるのだろう(あると思われている)が、必ずしもそうではないというのが、一般的な経験則だろう。しかしながら、現状では学歴以外に全体を通して妥当性のある指標がないのも確かだと思う。その結果、(特に中小企業等においては)新規採用だけではなく、中途採用においても、「何を見たらいいかわからない」状態か、「面接者によってばらつきがある」状況であり、「ある程度、ギャンブル的に捕らえている」例も少なくないのではないだろうか。
そういった意味においては、企業としても自社の社員で活躍している人たちの要素をインフォーマルな学習という観点から見てみる事は意義があることのように思える。簡単に言えば、「どんな経験をしてきたか」ということになるが、「どんな」という部分は会社によって違いがあると思う。
最後に、評価について思ったこと
かなり話が変わるが、感じたことを書きたいと思う。
学習成果の評価が本書における大きなテーマであるが、評価する対象としては、「ある人の現時点での知識、スキルなどの能力」という事になる。つまり、ストックとしての能力だ。資格試験も入学試験も学位の授与も基本的にはストックという事だ。一方、フローを見ることも必要だと思う。つまり、「いかに前よりも成長したか」という事だ。
学力低下などが叫ばれているが、国の政策などとは別として、「学力低下している人達」や「正規に教育を受けられなかった人達」は、自分たちで何とかしていかなければならないのが現実だろう。
その人達が、いかに学び続けるのかという時には、ストックとして、つまり現時点でどの程度学力があるかを評価したとしても、わかりきった現実を見せつけられるだけであり、次への意欲が生まれないのではないかと思う。そこで、「いかに前よりも伸びたのか」を示すことは、次への活力につながるのではないかと素朴に思った。
※本書の訳者である山形大学の松田先生より献本いただきました。ありがとうございました。