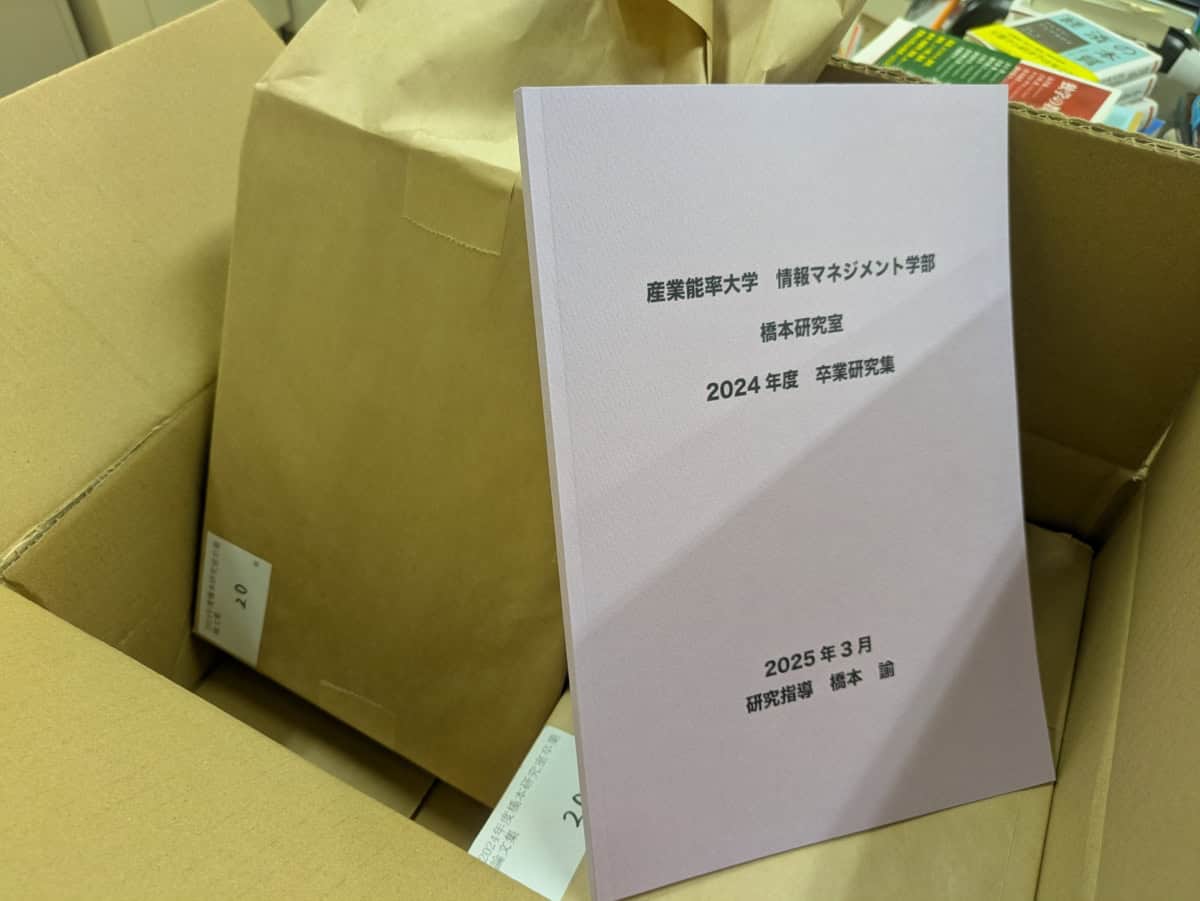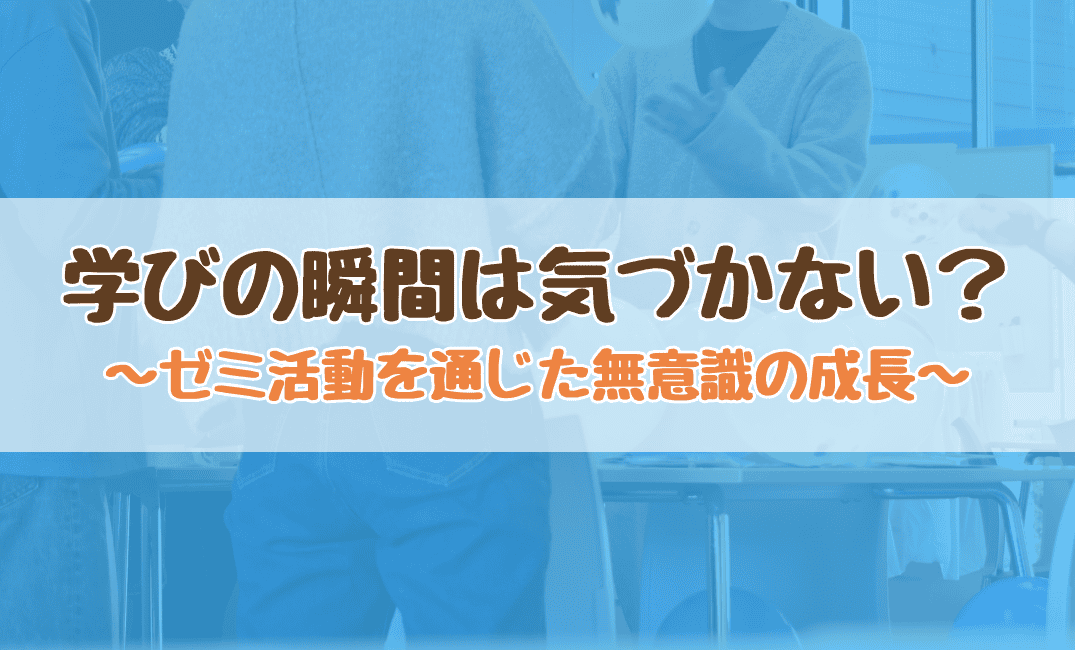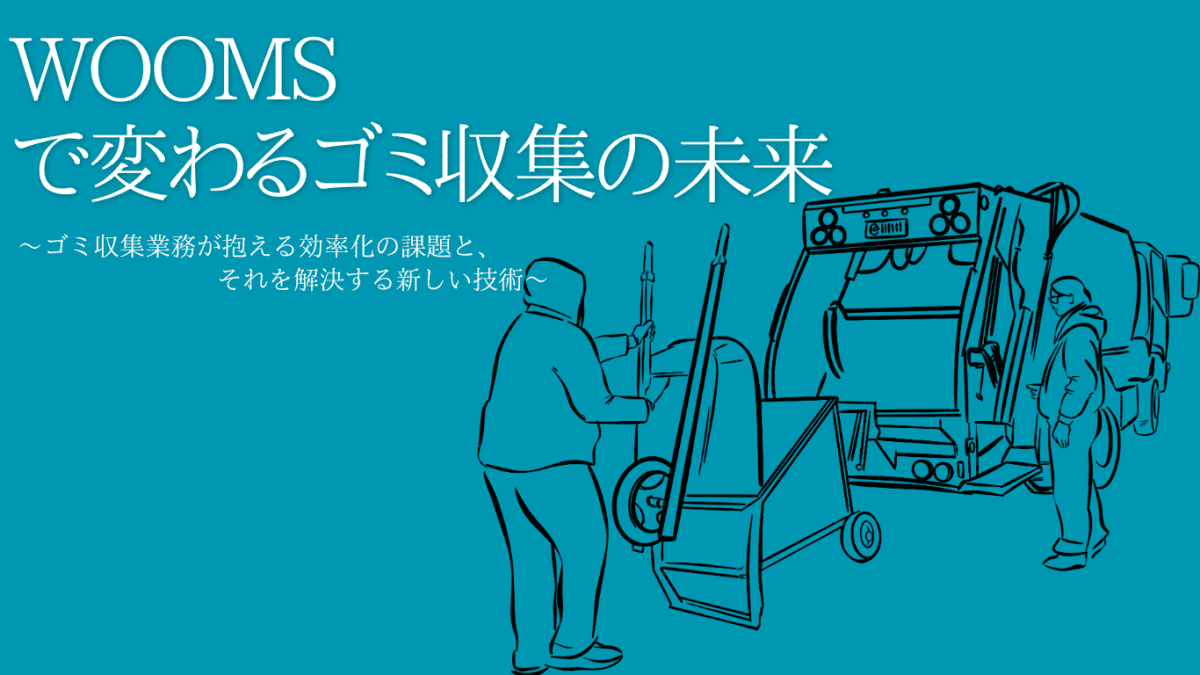2024年度の卒業式が行われ、橋本ゼミでも11期生が卒業しました。今年度はゼミとして過去最多である15本の卒業論文が提出されました。
本記事では、内容の一部を紹介いたします。
目次
組織開発の観点から見る飲み会 企業における飲み会の存在意義とは
庵 進之介
現代企業における「飲みニケーション」を組織開発の視点から分析した研究です。飲み会によって組織内の人間関係が強化され、士気やモチベーションが高まる効果がある一方で、強制参加や曖昧な目的設定が逆効果となる可能性も指摘しています。「飲み会」自体が文化ではなくなったコロナ禍を経た世代だからこその視点があります。
ボードゲーム制作者の創作動機に関する研究 ‐プレイヤー視点から探る制作者の動機‐
牛島 まどか
近年成長するボードゲーム市場に着目し、自主的に制作を行う方の活動への動機をインタビュー調査を通して明らかにした研究です。ボードゲームを作ることが大変なことであるとわかっているからこそ、なぜそんな大変なことをやるのか?を探究しています。「市場に理想のゲームがないので自作したい」「多くの人に楽しんでもらいたい」「制作そのものが好き」など多様な動機が確認され、ボードゲームが文化的・社会的価値も持つ可能性を示唆しています。
映像作品における女性キャリアの描かれ方についての研究〜作品からわかる女性キャリア形成における新たな障害〜
遠藤 亮
ドラマや映画などの映像作品を通して、現代女性のキャリア形成に影響を与える要素を分析した研究です。従来は出産や育児などのライフイベントが障害とされてきましたが、「恋愛」もキャリア形成を妨げる要因として描かれる傾向があることを大量のドラマの演出を分析することから指摘しています。
人はなぜルーツの無いスポーツクラブへ熱狂するのか? -欧州サッカーファンの非合理的なファン心理の調査-
小野 佑樹
歴史や地域的なつながりを持たない海外スポーツクラブが熱狂的ファンを獲得する理由を、欧州サッカーを例に考察した研究です。ファンは応援を通じて強い帰属感やアイデンティティを得ており、「非合理的(に見える)な熱狂」が何から得られているかを分析しています。
成果の見えにくい地域活性化を行うサークル活動が成立しているのはなぜか ―学内サークル「IPP246」の分析を通して―
川口 隆史
一見成果が見えにくい地域活性化活動を継続する大学サークルを事例に、活動が成立し続ける要因を分析した研究です。メンバー同士の主体的な参加やコミュニケーション、地域との連携といった要素が「ちょうど良い場合」に継続すると結論づけていて、過剰でも過小でもダメであると分析している点がユニークです。
大学の部活動を通じた能力開発の研究 -大学サッカーを通して身につけた能力は社会からも評価されるのか?-
櫻井 駿
体育会での経験が社会から評価されるのかを探究した研究です。中でも、同じような経験をしていても評価される場合とされない場合があるという点に着目し、体育会にどう関与するかによって差が生じることを自身の経験を踏まえて分析しています。
「親の受験」について塾講師の立場的ジレンマの考察〜中学受験が講師と生徒に与える影響の調査〜
徳永 祥太郎
加熱する中学受験において、そのステークホルダーの一人である塾講師の立場について調査した研究です。講師の置かれた立場や、生徒に寄り添おうとするが故に抱えるジレンマについてインタビュー調査をもとに明らかにしています。
なぜ教師は部活動指導に情熱を注ぐのか ―働き方改革と部活動指導の現実―
芳賀 美和
働き方改革が叫ばれる中、教師が部活動指導に大きな熱意を持つ理由を分析した研究です。長時間労働の是正が課題として浮かび上がっている中で、部活動が教師にとって自己実現や生徒との深い関係性構築の場となっていることを示します。現役教師へのインタビューから、現実の教育現場でどのように対処しているのかが見えてきます。
部活動の地域移行における問題点 高校部活動の観点から
原田 開
近年話題となっている部活動の地域移行に関する課題を分析した研究です。部活動といっても、中学校と高校は違うことや、種目による違いといった細部を見て行った際にどのような課題があるのかを明らかにしています。
企業におけるジョブクラフティングの誤用に関する研究〜ジョブクラフティング研修を通じた調査〜
福本 順也
自発的に仕事をより意義のあるものと捉える「ジョブクラフティング」が企業によって誤用されているのではという問題意識からスタートした研究です。企業研修に着目し、ジョブクラフティングが「単なる効率化」や「仕事の押し付け」にすり替わるケースを指摘しています。
ファミリービジネスの事業承継の成否を左右する後継者の主体性 経験者の振り返りインタビューからの分析
松崎 晃士
ファミリービジネスにおける事業承継を調査した研究です。株の移転といったテクニカルな事業承継ではなく、実際に承継ができているか?といったレベルでの承継プロセスを当事者へのインタビューを通じて確認し、後継者の主体性の重要性を明らかにしています。
運動部マネージャーの業務範囲拡張に関するオートエスノグラフィー
水沼 優那
運動部マネージャーとして活動している中で従来よりも役割を拡大させた際に生じた様々な「軋轢」をオートエスノグラフィーにより分析した研究です。経験を詳細に言語化することを通じて、想定読者である後輩へのメッセージになっています。
高校生有志の地域貢献団体が継続できる要因 -学生団体E4を事例に-
三宅 央二郎
高校生主体の地域貢献団体の継続要因を秦野市を中心に活動する学生団体「E4」の事例を通じて分析した研究です。現役生だけではなく、OBOG、関係者へのインタビューを行い、さらに活動に参与観察を行うことで多面的に分析しています。
組織のリーダーに必要な二重のリフレクション ―瑞木祭実行委員会の事例を中心に―
宮﨑 航太郎
大学祭実行委員会のリーダーを事例として、リーダーに求められる「自己内省」と「メンバーとの相互内省」を組み合わせた「二重のリフレクション」の重要性を示した研究です。それぞれのメンバーの「頑張った」という自己評価からどのように組織として(またリーダーとして)、レベルを上げていくのかを考察しています。
中学部活動における説教的指導は悪なのか ―経験者の振り返りインタビューからの分析―
原田 友翔
中学校の部活動で見られる強い叱責を伴う指導(説教的指導)について、多面的に検討した研究です。説教的指導自体は良くないものとされているが、一旦判断を留保し、指導者側へのインタビューを通じて、なぜ説教的指導を行うのかについて意図を捉えた上で分析をしています。指導者側、指導される側、またその間の立場といった観点から多面的に捉えています。
<卒業研究>
部活動におけるワーク・エンゲイジメントの考察 ―⾼校時代の経験とインタビュー調査をもとに― ⼤⽥⿓之介
同期意識はいかに⽣じ、どのような影響をあたえるか ―⼆つの学年のゼミを履修した学⽣の視点から― 桑原宏典