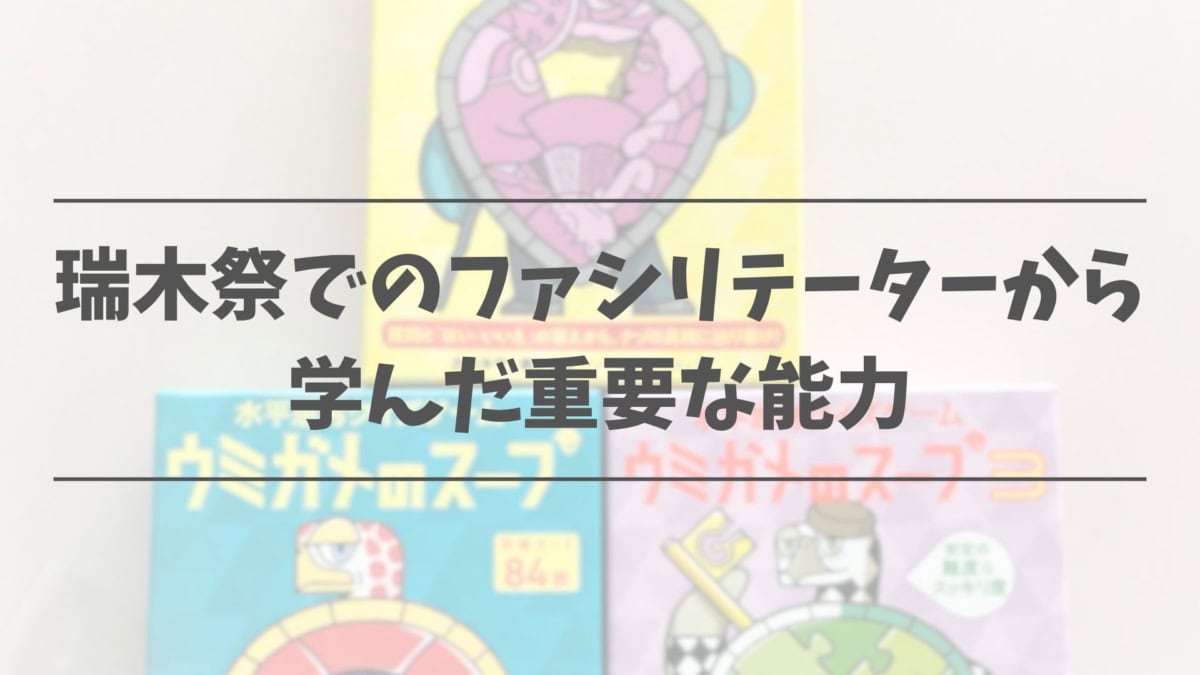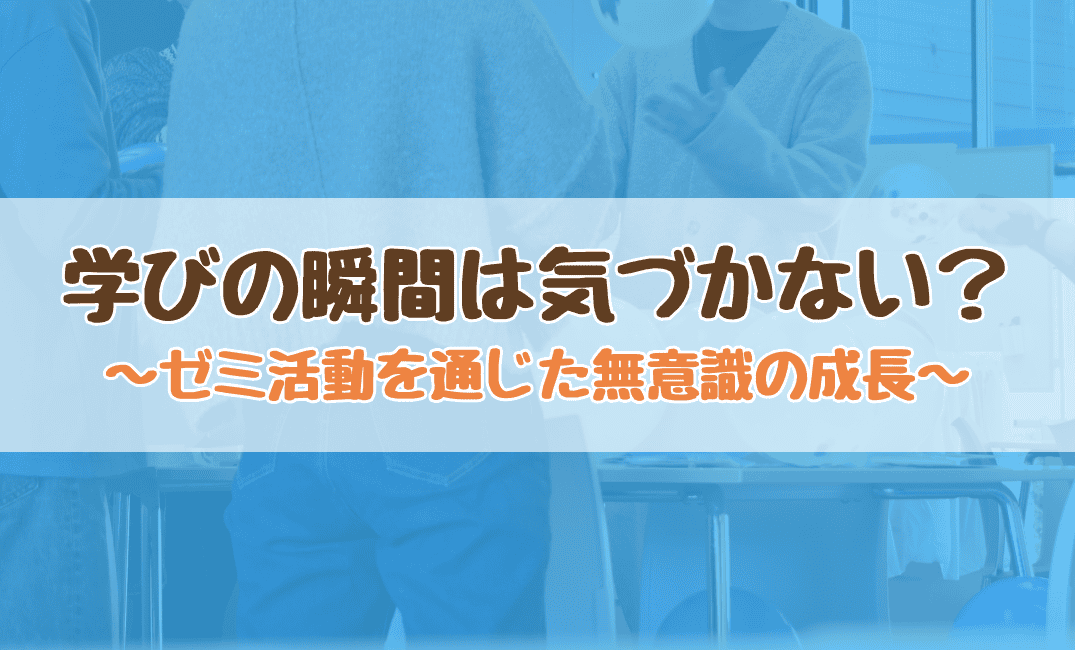目次
1. はじめに
橋本ゼミ13期生の富田望鈴と清水瑛大です。
私たちは11月に行われた学祭(瑞木祭)にて「Z世代のスチューデントエージェンシー」をテーマに研究発表を行いました。
私たちはウミガメのスープ×スチューデントエージェンシーのコンテンツを制作しファシリテーターを担当しました。この記事ではファシリテーターの難しさやアシストの方法をご紹介できればと思います。
2. 瑞木祭で行ったこと
私たちは、今回スチューデントエージェンシーを「ウミガメのスープ」というボードゲームで体験していただきました。
ウミガメのスープ とは水平思考クイズの一種で、ある物語や状況に対し、参加者が出題者に対し「はい」「いいえ」「関係ありません」のいずれかで答えられる質問をしていきます。あらゆる可能性を検討して真相を突き止めるゲームです。
ウミガメのスープの流れ
例題
二人の男が勝負をしていた。一人の男が空を見た瞬間に決着した。一体なぜ。
解答例
- 解答者:「二人は一対一で勝負をしていますか?」
- 出題者:「はい」
- 解答者:「空は晴れていましたか?」
- 出題者:「関係ありません」
- 解答者:「その場に審判となる人物がいますか?」
- 出題者:「いいえ」
・
・
・ - 解答:二人の男が勝負をして一人の男が空を見た瞬間に決着した理由は 「あっちむいてほい」をしていたから。
当日は参加者1~4人に対してファシリテーター(出題者)2人で進行しました。制限時間を5分に設定し、ヒントを1分ごとに出して問題を解いてもらいました。

3. ファシリテーターの役割
では、出題者であるファシリテーターの役割とは何なのでしょうか。
ファシリテーション(Facilitation) とは、英語の “facilitate”(促進する・容易にする)からきており、物事を効率的に促進したり、円滑に進めたりする働きを意味します。
そして ファシリテーター とはその役割を担う人を指します。
瑞木祭ではウミガメのスープの問題に徐々にヒントを出しながら参加者と一緒に取り組みました。何を質問したらいいのかわからない参加者に対して、ファシリテーターである私たちが質問の例を提示することで、質問をしやすい空間づくりを意識しました。
また、質問が出た際に「はい」「いいえ」「関係ありません」と答えますが、この場面でのファシリテーターの反応が非常に重要です。
受け答えの言い方や表情によって、参加者は自分の回答が答えにどれくらい近いのかを判断します。
このように、ファシリテーターは その場の話し合いを活発化させ、参加者がテーマに取り組むように促進すること が役割です。

ファシリテーターの練習風景
4. 瑞木祭でのファシリテーターの難しさ
一般的な会議のファシリテーションと瑞木祭でのファシリテーションの違いを比較し、難しさについて考えます。
難しい点:参加者の違い
- 一般的な会議のファシリテーション
- 事前に誰が参加するかを把握できる
- 参加者はファシリテーターの存在を認識している
- 瑞木祭でのファシリテーション
- 来場者が誰なのか分からない
- 参加者はファシリテーターと初対面の状態で質問をする必要がある
このため、質問をする空気づくりがより難しくなり、ファシリテーターの存在の重要性を実感しました。
また、子どもから大人まで幅広い年齢層の方が参加するため、対応力が求められる のも難しさの一つでした。
5. ウミガメのスープにおけるアシストの仕方
ウミガメのスープのファシリテーターとして、参加者が解答へ辿り着くアシストの理想的な方法について考えます。
1. 即興力を高める
即興力を高めるためには事前の準備と進行の工夫が重要 です。
事前準備
- イントロダクション・問題・解説を完全に理解し、言葉の言い回しを工夫する
- 大人向けと子ども向けで説明の仕方を変える
- 質問の予測
- 事前にどのような質問が来るかを予測し、返答の候補を用意する
進行の工夫
- 情報の可視化をする
- ホワイトボードまたは紙を用意し、参加者の質問と回答を記録
- これにより、思考の整理がしやすくなり、新たな質問が生まれやすくなる
また、ファシリテーター2人で役割を分担 し、一人は進行役とタイムキーパー、もう一人は情報の整理と可視化を担当することでスムーズな進行が可能になります。

問題を共有する様子
6. まとめ
以上から、ウミガメのスープにおいてファシリテーターとしての役割を果たすには、事前準備 と 進行中の情報可視化 を行い、「即興力」を強めることが重要です。
「即興力」を鍛えることでファシリテーターに限らず、さまざまな場面で活用することができます。
皆さんもぜひ、ファシリテーション力を磨いてみてはいかがでしょうか。
参考文献
安斎勇樹、塩瀬隆之, 『問いのデザイン 創造的対話のファシリテーション』, 学芸出版社, 2021年
執筆:橋本ゼミ13期生 富田望鈴 清水瑛大